長野県内の生協のさまざまな活動・事業を紹介します。
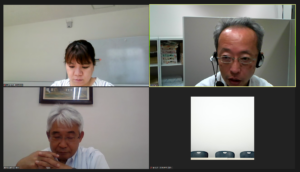
2023年7月12日(火)10時00分よりオンライン会議として2023年度第1回医療部会が開催されました。東信医療生協、上伊那医療生協、県生協連事務局を含めて4名が出席しました。
※会議に先立ち参加者全員が一堂に会するのと同等に充分な意見交換ができることを相互に確認しました。
冒頭、今年度の部会長に藤沢薫専務理事(東信医療生協)を選任し、藤沢部会長が挨拶の後議事を進行しました。
(1)2022年度第3回医療部会報告
(2)2023年度介護福祉部会報告
(3)信州まるごと健康チャレンジ企画概要
(4)協同組合フェスティバル2023は2023年10月1日(日)の開催概要の報告
・事務局より資料に沿って報告を行い確認しました。また、協同組合フェスティバルについては、長野医療生協の出店情報の共有をお願いしたい旨発言がありました。
(1)2023年度の取り組みについて
① 部会の開催については、年3回開催することとしました。
日 程:第2回 2023年10月 11 日(水)10:00~ 会場:オンラインで実施(予備日10/13)
第3回 2024年 1 月 12日(金)10:00~ 会場:オンライン又は実参加で実施
② 県外視察について
・県外視察について、コロナ終息とは言えない現状で考えにくいです。
・視察研修という点では、近年災害が多発する中で、介護施設のBCP作成も義務化されていることもあり、
防災や減災、災害に備える準備、BCPなどについて学習や交流のニーズがあります。
・災害時の生協間の支援物資の融通など、出来ることがあるかどうかの協議検討したいとの発言がありました。
・在宅で人工呼吸器を使用している患者さんや介護施設を利用している利用者さんへの対応も課題。訪問介護の利用者さんなども、何の医療機器を使用しているのか?災害時の対応としては、ケアマネジャーさんとも対応について共有して行く必要もある。個別避難計画の作成も努力義務化されているとの発言がありました。
・令和元年東日本台風災害時の豊野地区の賛育会の事例を聞いたことがあった。実際の事例を参考にしたい。長野県社協の災害時に活用できるマップシステムを進めています。今後どういう視察研修が可能か検討していくこととしました。
③ 信州まるごと健康チャレンジ2022のキックオフ学習会の計画について共有しました。
④県生協連主催の職員交流集会、ファシリテーション講座、理事長・専務理事懇談会、協同組合連絡会主催の
これからの協同組合を話し合うワークショップについて共有しました。
(2) 活動交流について
・各会員生協より、前年度の決算状況、総代会開催状況、2023年度の4月~5月状況を交流しました。
次回部会日程 10月11日(水)10:00~ オンラインにて実施予定。

7月11日(火)13時00分からホテルメトロポリタン長野の3階飯縄の間(長野市)において、監事・理事研修会が開催されました。講師には日本生活協同組合連合会渉外広報本部法務部監事監査支援担当の井藤康治氏をお迎えして、4会員生協と事務局を含めて14名が参加しました。
今回の研修会は監事監査について1から学びたい人を対象に、生協法に規定されている監事の職務及び権限などについて理解し、監事監査の基本事項を学ぶ研修会として開催し、監事監査の全般(職務、権限、義務、基本スタンス)を学ぶ内容です。
前半は2時間の講義です。1.監事の職務の基本(生協法を意識して)、2.業務監査の基本、3.会計監査の基本、4.監査報告書の作成、5.関連資料の紹介の内容です。2007年に約60年ぶりの生協法の改正により、生協の機関運営の強化と明確化が図られ、その中で監事は理事の職務執行を監査する機関として位置づけられています。監事としての基本的な義務について、監事の善管注意義務について、監事監査の目的について話されました。
業務監査では、理事が善管注意義務を尽くして職務執行しているか、及び法令・定款・総代会決議を順守して職務執行しているかが監査の対象です。監査報告に求められる記載事項や業務監査の内容の説明がありました。
また理事会などの重要な会議への出席に関しては、出席する前の調査、会議の場における監査、理事会後の調査の説明があり、監査体制の整備や理事や職員から報告受領などが重要であることなどの話がありました。
会計監査の基本では、まず監事の会計監査の目的の説明があり、理事が作成する報告書の信頼性を担保するものとして、監事の監査があり、独立した監事の監査を受けた報告書だから総代も承認してよいかどうかの判断材料になると説明されました。監事の監査について1年間の流れの説明があり、監査計画と監査報告書の作成についての説明がありました。
参加者の声としては、「監事の役割の全体が理解できた」、「監事の基本的な役割、やるべきことが学べました。重要でやりがいのあるポジション、仕組みだと思いました。グループ交流でも他生協の取り組みを知ることができて有意義でした」、「生協法の振り返りができて良かった」、「新任の頃に同じような内容の学習をして、あまり理解できなかったのですが、今回の講演をお聞きして、だいぶ理解できたのが嬉しかった」、「監査方法をわかりやすくお話いただけて良かった」、「監査の業務、責任などよく理解でき、頭の整理が少しできた」、「理事にも学んでほしい」などが出された。

原水爆禁止2023年国民平和大行進は、核兵器のない世界をよびかけ、ストップ戦争準備、日本の核兵器禁止条約参加を求める、最大の国民的運動です。長野県生協連は事務局団体として参加しており、関佳之専務理事が代表委員の一人になっています。
世界に目を向けると、ロシアのウクライナ侵略が続き、核兵器使用の威嚇も繰り返されています。米国も中国も北朝鮮も軍事力を増強し、朝鮮半島や台湾をめぐって軍事対軍事、核対核の軍事体制強化が進められ、緊張が高まっています。
核廃絶は人類の明るい未来のために、ぜひともなしとげなければならない課題です。世界の人々の平和とよりよい生活のために、戦争や被爆の実相の継承を着実に進め、平和と核兵器廃絶への願いを広げていくことが求められています。
5月7日に北海道の礼文島を出発し、スタートしました。多くの国と地域から「核兵器のない世界」を求める人々の声が大きく広がっている中で、国民平和大行進は全国各地から広島・長崎に向け、平和と核兵器廃絶を願いながら誰もが参加できる行動として66年間続いています。今年は6月30日に新潟県から引き継ぎ、県内を縦断して7月7日群馬県へ、7月12日山梨県へ引き継がれます。
7月4日(火)には、長野県庁前にて出発式が行われ、清水幸弘県教組委員長が主催者あいさつ、稲玉稔長野県国際交流課長の激励メッセージや佐々木祥二長野県議会議長からのメッセージが紹介されました。その後、県生協連 関佳之専務理事が、核兵器の廃絶願いを込めてメッセージを発表しました。長野県生協連からはペナント協力も行いました。
今年の長野県での行進は、4年ぶりに県内各地での網の目平和行進が再開されています。最後に、今年度の取り組みと情勢について、長野県原水協の丸山実事務局長から報告がありました。その後、全員で長野バスターミナル会館に向けて平和行進が行われました。

7月4日(火)に長野県生協連主催の上期研修会「日本生協連2030ビジョン第2期中期方針及び協同組合のアイデンティティに関する学習会」を開催し、4生協及び事務局含め37名の参加がありました。講師には日本生協連の二村睦子常務理事をお迎えして、『「地域との未来共創」をめざす生協のとりくみ』と題してご講演をいただきました。
県生協連の太田会長の主催者挨拶の後、JCA(日本協同組合連携機構)作成の「協同組合のアイデンティティに関するICA声明」について考える動画(16分)を視聴し、二村常務の講演に入りました。
講演では地域づくりの現在地として、1995年に協同組合原則に「7.コミュニティへの関与」が追加され、協同組合は地域を離れられないし、地域の社会や経済を回す存在であるということ。地域活動の様々な実践の中で、明らかになってきたこととして、「行政や地域の諸団体と連携することで、生協の強みを生かして地域の問題の解決につながる」、「連携することで、生協自身が、生協の強みと弱みに気づくことができる」、「連携を通じて、地域の課題やニーズに気づくことができ、新しい事業や活動の種が生まれる」と。
今、民間企業がSDGsの取り組みを含め「生協」っぽくなってきている。こうした企業の動きと私たちを分けるものは何か?「協同組合原則」⇒「私たちはこの原則を生かした生協になっているでしょうか?運営において、事業や活動の実践において、と呼びかけられました。これからの社会やくらしの変化で特に着目しているものとしては、人口減少・世帯数減少・超高齢化に伴う市場縮小と競争の熾烈化。もう一つは、地球環境や社会の持続可能性に迫る危機がコロナ禍やウクライナ情勢により加速化していること。
生協の年代別の世帯加入率では20代~40代で減少している。晩婚化・晩産化・未婚率上昇の影響と考えられる。コロナ禍を経て、生協の食品小売シェアは実は0.3ポイント減少している。第2期中期方針の基調としては、「足場づくり」を強め、次の第3期に向けての「飛躍への一歩」を踏み出すこと。この3年間に上記の環境変化の中で、これらの危機に根本的に対応する変革を起こせなければ、生協の価値を未来につないでいくことは困難になります。ビジョン実現に向けた変革のラストチャンスと話されました。
この変革に関連する事例として全国各地での取り組みをご紹介いただきました。また生協の持つリソースを地域に役立て、行政との協定や災害時の協定は全国に広がっています。福岡県のフードバンク協議会、茨城県の協同組合ネットいばらきのとりくみ、ならコープの「かわかみらいふ」との提携、おかやまコープの道の駅での商品の販売、鳥取県生協の団地自治会が運営する店舗への商品供給、コープぎふの市・公共バスと協働で「貨客混載事業」、コープさっぽろのスクールランチ事業、パルシステムの予備青果のフードバンク等への提供、コープこうべのあまがさき住環境支援事業「REHUL」、大阪いずみ市民生協のまちのリビング「すきいま」、ララコープの「ララ元気ねっと」、いばらきコープの「学校教育に役立つ学習プログラム、コープこうべのちいきつながるミーティングなどご紹介いただきました。
参加者からは「実際の数値で生協の現状を知ることができ、課題が見えてきました。創造性とイノベーションんを発揮することが求められているということで、他生協のとりくみ事例なども参考に「これから私たちにできること」をしっかりと考えていこうと思います。いろいろとヒントになる貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました」など前向きな多くの感想が寄せられました。
(写真:上は学習会の様子、下は講師の二村睦子常務理事)
★学習会冒頭に視聴した「協同組合のアイデンティティに関するICA声明」について考える動画(16分)は 右記URLからご視聴いただけます。⇒ https://www.youtube.com/watch?v=RIIm7cOXUto

6月30日(金)長野県虹の会は、ホテルメトロポリタン長野2階「梓の間」(長野市)において、第35回定期総会を開催しました。
同会は、長野県にゆかりのあるCO・OP商品の製造流通に関わるお取引先様24社と県生協連やコープながの、信州大学生協、セイコーエプソン生協の28会員で構成されています。今回の定期総会には18会員24名が参加しました。
定期総会は、大谷昌史会長(信越明星㈱代表取締役社長)の挨拶に続き、県生協連の太田栄一会長理事が挨拶を行いました。議長には、大谷代表世話人が選任され議事を進行しました。議事では、関佳之事務局長(県生協連専務理事)が第1号議案「2021年度及び2022年度活動報告」、第2号議案「2023年度活動計画」、第3号議案「役員の任期延長の件」について説明提案を行いました。その後行われた採決では、全議案が可決承認されました。活動報告の中では、昨年の協同組合フェスティバルへの会員企業の参加・協力についても報告されました。
その後、日本生活協同組合連合会の執行役員・第二商品本部長の藤本友子様の講演会が行われました。講演では「全国の生協の状況と日本生協連のCO・OP商品政策」と題してお話をいただきました。
また、事務局から、10月1日(土)に長野市表参道セントラルスクゥエアで開催される「長野県協同組合フェスティバル2023」への協力のお願いや「信州まるごと健康チャレンジ2023」の紹介、フードバンク信州への食品提供などの話がありました。すべての議事を終了し、内田信一副会長(長野県農協直販㈱代表取締役社長)より閉会の挨拶がありました。定期総会終了後は、会員相互の交流を深めることを目的に交流懇親会を行いました。