長野県内の生協のさまざまな活動・事業を紹介します。
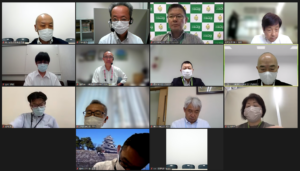
2022年6月20日(火)13時30分からWEB会議システムにより第1回理事会が開催され、会長・副会長を含め理事10名、監事2名が本理事会に出席しました。
なお、議事に先立ち理事会参加者全員が一堂に会するのと同等に充分な意見交換ができることを相互に確認しました。以下の議題が承認、確認されました。
13時30分、関佳之専務理事が開会を宣言し、太田栄一会長理事が挨拶を行い、理事会規則第7条により議長に山本佳道副会長理事が選任さました。冒頭、先日の総会で選任された田島理事と井出監事よりご挨拶を頂いた後に議事に入りました。14時20分にすべての議事を終了し閉会しました。
≪議決事項≫
1.副会長の互選に関する件
関専務理事より副会長の互選に関する件について提案があり、協議を行いました。協議の結果、提案の通り承認しました。
2.2023年度の理事の代行順に関する件
関専務理事より2023年度の理事の代行順に関する件ついて提案があり、協議を行いました。協議の結果、提案の通り承認しました。
3.2023年度渉外・連携等に関する役割分担の件
関専務理事より2023年度渉外・連携等に関する役割分担の件について提案があり、協議を行いました。協議の結果、提案の通り承認しました。
4.2023年度役員報酬委員選任の件
中谷事務局長より2023年度役員報酬委員選任の件について提案があり、協議を行いました。協議の結果、提案の通り承認しました。
5.2023年度役員推薦委員選任の件
中谷事務局長より2023年度役員推薦委員選任の件について提案があり、協議を行いました。協議の結果、提案の通り承認しました。
6.2023年度7月以降の役員報酬に関する件
太田会長より7月以降の役員報酬に関する件について提案があり、協議を行いました。協議の結果、提案の通り承認しました。
≪協議事項≫
関専務より口頭で、当初予定の沖縄県視察の日程調整不調のため、断念することの報告がありました。中谷事務局長より代替案として、被災地視察及び該当県連との交流を内容とする理事会県外視察の企画の提案があり、協議を行いました。協議の結果、代替案の内容で企画を準備することとしました。
≪報告事項≫
以下の事項を事務局が報告し、了承しました。
1.機関会議等報告
(1)第1回常任理事会
(2)5月度決算概況
2.その他報告
(1)今後の各研修・懇談会等の企画について
(2)各種研修・懇談会のまとめ
(3)災害対策協議会
(4)会員活動担当者交流会
(5)協同組合連絡会幹事会
(6)消団連幹事会
(7)2023長野県平和行進
(8)県連ニュース
3.情報提供
(1)フードバンク信州:フードドライブニュース
(2)災害復興支援&防災減災ニュース
(3)生協とワーカーズ連携ニュース
(4)【当日資料】令和5年度の消費生活協同組合指導検査について(通知)の報告がありました。
以上をもってすべての議事を終了し、議長が14時20分に閉会を宣言しました。
2023年6月13日(月)9時00分よりオンラインにて会員活動担当者交流会を開催し、コープながの、生活クラブ、信州大学生協、住宅生協、パルシステム山梨、事務局より7名が出席しました。冒頭、事務局が開会挨拶を行い、その後、交流会の議事を進行しました。
なお、議事に先立ち実行委員参加者全員が一同に会するのと同等に十分な意見交換ができることを相互に確認し、議事に入りました。
◆会議内容・議題
1.前回の議事録の報告をしました。
2.2023年度の研修会などの開催計画について
・7/4の上期研修会の案内を行った。企画内容として日生協2030ビジョンの第2期中期方針と協同組合のアイデンティティに関する声明の学習会であり、参加を呼び掛けました。
・7/11の監事・理事研修会の企画説明と内容を紹介した。監事監査の基本と監査のポイントについての学習であり、理事も参加対象として、後半には参加者の交流タイムもあり、参加を呼び掛けました。
・7/18の信州まるごと健康チャレンジのキックオフ学習会について、現在の企画準備状況を報告共有しました。
・7/27のファシリテーション講座(応用編)の内容を説明共有し、参加の呼びかけをしました。
・7/13の職員交流集会の案内を行い、参加を呼び掛けました。
・2023年度の学習会・研修会・懇談会企画について年間スケジュールについて報告しました。
・【協同組合のアイデンティティについてのワークショップ】企画について8月22日(火)JCAの前田健喜部長を講師にお迎えして、JAビル12A会議室にて13時~16時に開催することを報告共有しました。
・【地域共生社会づくり研修交流会】企画について9月22日(金)上野谷佳代子氏をお迎えして、長野県総合教育センター(塩尻市)を会場に開催する。企画検討会議が始まったことを報告共有しました。
3.会員交流~主な内容
〇生活クラブ生協長野:生協内でワーカーズコレクティブの立ち上げを進めており、現在組合員及び職員向けに学習会を行っています。地域課題に取り組む自主事業系の取り組みも始まっている。また生協事業の受託事業として、上田地区の配送ワーカーズが2023年2月よりスタートしています。
〇コープながの:平和学習(7/21マツシロ・9/12満蒙開拓)をオンライン企画で予定。食の安全学習会も開催予定。総代会に向けて、バス企画や試食も復活して準備しています。
〇住宅生協:長野地区では労働金庫の協力も得て、7/29~30に長野市エムウェーブにて住宅フェアを開催予定です。
〇大学生協:5月に総代会済み。県立大は関根さん、松本大は杉山さん、看護大は橋本さんの担当となります。信州大学は田島専務、長野大学は小谷専務、清泉女学院は小谷専務が理事を務めていて、森山店長が職員として勤務しています。
〇労働金庫:8月にコープながのとイデコの昼休み学習会を実施。2025年に共学になる予定の清泉女学院生協と何か一緒にできないか検討中です。
〇パルシステム山梨:6/15に総代会。今年度はお米の自給率をテーマにしています。居場所づくりの活動では子ども食堂や貧困支援に取り組んでいる。今後地域の居場所づくり活動を広げたいです。
4.その他、次回会議日程、7月13日(木)9:00~、ズームによるオンライン会議を確認しました。

2023年6月8日(木)16時00分より、オンライン会議システムにて、長野県協同組合連絡会第2回幹事会が6団体8名の参加で開催されました。JCAより片岡氏にも参加いただきました。定刻になり、中谷隆秀事務局の開会宣言の後、関幹事長が挨拶を行い、その後議長を務め議事を進行した。
関幹事長より通常総会が滞りなく終了した旨、報告がありました。小山城也事務局長より総会終了及び総会での負担金確定の報告と6月末までの送金について連絡がありました。総会後の懇親会費用について後日各構成団体に請求書をお送りする旨報告がありました。
〇JCAの片岡昇氏より、2023年度全国に呼び掛けているワークショップの位置づけ、ICA(国際協同組合同盟)からの提起を受けての意味と内容について、丁寧に説明をいただきました。
・約30年サイクルで時代の変化を踏まえた協同組合のアイデンティティの論議・見直しが行われてきた。
・国際的な論議への参加の意義、
・現在の協同組合の現状の確認と原点を見直し学ぶ機会。
・これから20年、30年先の協同組合を考えるきっかけ。
・他の協同組合の考え方をワークショップで共有することが、自組織の組織発展の刺激になる事も期待。
・50名~110名の参加規模でのワークショップを想定している。(1構成団体から5名~10名の参加規模)
〇事務局より上記提起を受けて、8月22日のワークショップ企画の実施に向けて提案があり、全員で確認しました。
事務局で協議を行い、日程調整後後日案内することとしました。
以上

長野県協同組合フェスティバル2023第2回実行委員会が6月8日(月)13時30分からJAビル4階会議室にてハイブリット形式にて開催され、11団体から17人が参加しました。関事務局長(県生協連専務)が開会の挨拶を行い議事を進行しました。
◆協議事項
事務局が前回の実行委員会報告を行い確認しました。
事務局が資料にそって提案し協議を行った。協議の結果、出店内容に(試食・試飲は可)を追記することとし、開催概要を確認しました。後日、確定した開催概要を事務局が配信することとしました。
前回実行委員会で出された意見についても、協議を行い以下の対応を確認しました。
・開会式は行わない。参加者アンケートはQRコードによる回答を中心とする。事前に表参道秋祭りと情報交換を行う。また、レイアウトや陽当たりなどについては、今後レイアウトの検討の際に協議することとしました。
事務局が「出展ご協力のお願い」文書を提案し、協議を行った。協議の結果、提案の通り確認しました。
「水風船の配布と参加の呼びかけ」と「参加者アンケートの回収と景品交換」の2つを行うことを確認しました。昨年粗品として準備したうまい棒が余り、水風船と一緒に配布して喜ばれたとの発言があり、今年度についてどうするかは景品交換の景品の集まり具合などを考慮して検討することとしました。
昨年のデザインは良かった。今年度のデザインは次回協議検討することとしました。
次回第3回の実行委員会は7月21日(金)に行う。時間は13時15分にJAビル4B会議室に集合して、13時30分から会場(長野市のセントラルスクゥエア)の下見をする。会場に13時30分集合でも良い。その後、JAビルの会議室に移動して、14時30分~、第3回実行委員会を開催する。ハイブリッド形式で開催します。
次々回第4回の実行委員会は、8月22日(火)9時30分~10時30分に、JAビルを会場に、ハイブリッド形式で開催します。その日の午後は、協同組合連絡会のアイデンティティについての学習会の予定です。
10/1フェスティバル当日、11/7第5回とします。
以 上

信州まるごと健康チャレンジ2023第3回実行委員会が6月8日(木)15時00分からWEB会議システムにて開催され、10組織から16人が出席しました。定刻になり事務局が挨拶を行い実行委員会の関事務局長(県生協連専務理事)が議事を進行しました。
事務局が前回実行委員会の議事録の説明を行い、確認しました。
〇後援取得状況について
⇒現在集約中で、順調に取得できています。
〇パンフレットの原稿の確認とチェックについて
⇒実施団体の記載で、「企業組合労協ながの」⇒「労働者協同組合ワーカーズコープながの」に修正。また、
実施団体に長野県社会福祉協議会を追記。「チャレンジコース⑨で、子どもチャレンジに挑戦しよう!」
を「キッズチャレンジ、親子で挑戦しよう!」に変更します。
〇景品のオリジナルデザインと色の検討について
⇒昨年のデザインを踏襲し、2022を2023に修正する。色はオレンジに決定。
〇各団体の部数集約について
⇒JA長野中央会は2880部だが、本部分を検討して後日連絡する。ワーカーズコープながの1000部、ワー
カーズコープ信州400部、生活クラブ生協ながの1000部、上伊那医療生協15000部、労働金庫1000部、
こくみん共済coop500部、東信医療2500部、その他未報告団体については、6月14日(水)までに事務
局に連絡することとしました。また、全体の部数を集約後、一般や行政、関係団体への配布分として事務局分部数を調整すること、各団体の報告部数で不足した場合には事務局分を無償で配布することを確認しました。
⇒事務局より内容は昨年同様とし、信州ACEプロジェクトのデータを追加するとの提案があり、確認しました。
⇒事務局より、本年度もメールマガジンの発行の提案があり、確認しました。
⇒事務局より、昨年同様に各構成団体に向けて発信する方向で会長と調整するとの提案があり、確認しました。
⇒6月13日13時30分~、運営スタッフの打ち合わせ会議を県立大学3階B30番教室で行います。
各構成団体の参加枠について、ワーカーズコープながの2人、生活クラブ生協2人、長野医療生協は人数増も可能。東信医療生協2~3人、上伊那医療3人、県社協3人と報告があった。今後全体人数を見て事務局が調整することとしました。
7月21日(金)16時~17時、JAビル4B会議室(ハイブリッド形式)にて開催することとしました。
8月22日(火)10時30分~11時30分、JAビル(ハイブリッド形式)にて開催することとしました。尚、8/22は午後に、長野県協同組合連絡会主催の協同組合のアイデンティティの学習会があります。
以上