長野県内の生協のさまざまな活動・事業を紹介します。

長野県協同組合フェスティバル2022年度第3回実行委員会が6月9日(水)10時00分からオンラインにて開催され、14団体から21名が出席しました。定刻になり中谷事務局が開会を宣言し、実行委員会の関佳之事務局長があいさつと後、議事を進行しました。議事に先立ち参加者全員が一堂に会するのと同等に充分な意見交換ができることを相互に確認した。
◆会議内容
事務局が前回議事録の報告を行い、全員で確認しました。
・開催概要と出展者募集に関して、資料にそって事務局が説明を行い協議しました。協議の結果、開催概要修正案を確認した。ライブ配信を中止とし、動画の配信を行うこととしました。動画の作成及び提出については強制としないことを確認しました。
・屋内ブースと屋外ブースの準備については、屋内ブースの希望がなく、屋外の点とブースのみの企画とすることとしました。
・出展者募集の案内について確認しました。
・駐車場の確保(無料で使える駐車場の提供)の希望が出されました。会場周辺での場所の確保が困難なこともあり、出展者や参加者には駐車場はないことのお知らせをすることとしました。また県庁の北側と南側と議会棟の各駐車場は土曜日と日曜日は一般開放されていることの情報も共有しました。併せて、出展者への案内では周辺の有料駐車場の案内も含めて、丁寧な案内をすることとしました。
・会場であるセントラルスクゥエアの多目的スペースの21台分の駐車スペースは、出展者の搬入・搬出場所として確保することを確認しました。
資料にそって説明し共有しました。広報チラシは8月末頃の完成を目指すこととしました。救急対応での看護師の手配については、今年度は行わないこととしました。実行委員会企画については、参加者アンケートを実施することと、一般の方の呼び込み、子ども連れの参加者増を目的にした工夫を次回実行委員会で協議することとしました。
第4回実行委員会 7月21日(木)10時~11時 出展企画の決定(出展募集7/15〆切)、告知チラシ原稿協議
第5回実行委員会 8月24日(水)10時~11時 当日運営体制、レイアウト図、告知チラシ完成
第6回実行委員会 11月に開催予定 フェスティバルのまとめ
次回実行委員会日程:7月21日(木)10時00分~ 会場の下見を兼ねて実参加開催とするか、たオンライン開催とするかは後日案内することとしました。

2022年6月8日(水)10:00よりオンラインシステムにより第1回介護福祉部会を開催し、長野医療生協、投信医療生協、コープながの、上伊那医療生協、高齢者生協及び事務局より8名が出席しました。会議に先立ち2022年度の部会長の互選を行い豊田孝明氏が部会長に選任されました。その後、豊田部会長が挨拶し、議事を進行しました。部会開始に先立ち参加者全員が一堂に会するのと同等に充分な意見交換ができることを相互に確認した。
◆会議内容
・長野医療生協の豊田孝明氏に介護福祉部会長を推薦する意見が多く、本人の承諾を得て部会長を選任しました。
・第5回部会の議事録について事務局が報告を行い確認しました。
昨年同様に年間5回の開催とする。日程は各参加者の予定を調整して、以下の日程に確定しました。
第2回7/20(水)10時~、第3回9/12(月)10時~、第4回12/14(水)10時~、第5回2/17(金)10時~。
・実参加の企画を開催する際には部会と合わせての実施を基本とすることとしました。
・上伊那医療生協の看多機施設への視察を計画することとしました。
・チームマネジメントやファシリテーション講座
⇒6/30開催のファシリテーション講座の案内をすることを確認しました。
・クレーム対応研修、VR体験研修会、
・介護事業所の役割や認知症を学ぶ、介護の基本を知る学習会の開催。
※第2回部会にて、今後具体化していくこととしました。
コロナ禍が続いておりイメージが持てない状況です。以前視察した「あおいけあ」の視察は参加した職員の大きな刺激になりました。地域包括ケアの実践例の視察。先駆的な事例より、足元を見て今後の事業に活かせる、今後の生き残りのヒントになる視察が良い。「暮らしネット・えん」の視察など。
第2回部会で継続して協議することとしました。視察方法のアイディアとしては、現地視察するメンバーと現地とオンラインで結んでライブ配信で参加するメンバーとに分けて、実施する方法など意見がありました。
2,3年できていない懇談機会について協議した結果、行政との懇談機会は重要であることから、今後継続して部会の中で実施の方向で検討していくこととしました。
現在行政の介護計画も予定通りでない現状もあり、地域でも事業継続が厳しい状況も生まれている。長野市や松本市は中核的な市でもあり、その動向が周囲の市町村にも影響を与えている。行政とのコミュニケーションの機会は大切なので、今後検討していくこととしました。
4.会員交流
各会員生協より資料にそって交流した。通所の入浴加算2について情報共有を行いました。
5.次回会議の確認
以下の日程を7月20日(水)10時~と確認しました。

長野県生協連は、 6月2日(木)14時よりメトロポリタン長野(長野市)にて「第71回通常総会」を開催しました。今年は昨年同様新型コロナウィルス感染症の拡大防止や参加者の安全を第一に考え、例年ご出席いただいている来賓の皆さまにはご参加頂かず、各会員の代議員の皆さまには書面出席を主とする総会運営にご協力をいただく中で開催されました。
冒頭、関根明副会長理事が開会の挨拶を行い、議長に長野県労働者共済生協の川島宏夫代議員が選出されました。太田栄一会長理事の主催者挨拶に続いて、資格審査報告が行われ、代議員定数27名に対し実出席5名、書面出席22により総会の成立が報告され、議案審議を行いました。
第1号議案から第4号議案を関佳之専務理事が提案し、草野永典監事が監査報告を行いました。各議案は以下の通りです。
第1号議案「2021年度のまとめ、決算書及び剰余金処分承認の件」
第2号議案「2022年度活動方針、及び予算決定の件」
第3号議案「役員選任の件」
第4号議案「役員報酬決定の件」
質疑では意見や質問はなく、その後の採決ではすべての議案が賛成多数により可決承認されました。議長が総会の閉会を宣言し、関根明副会長理事が閉会の挨拶を行いました。
総会後、新たに理事に選任された長野県労働者共済生協の大好博巳専務理事、長野県農業協同組合中央会の北島直樹総合企画室室長、生活クラブ生協の草野永典常務理事、コープながのの込山晴美理事、上伊那医療生協の高橋誠理事(欠席)と監事に選任されたコープながのの渡辺実執行役員が紹介されました。また、今総会で退任されます小林孝子理事、清野みどり理事には記念品と花束の授与が行われ、それぞれ退任のご挨拶をいただきました。また、例年開催されていた総会後の懇親会は中止としました。
2022年5月30日(月)13時30分より、オンライン企画にて、2022年度第1回学生総合共済PJが開催され、コープながの、信州大学生協、県生協連に加え、オブザーバーとして、コープ共済連、大学生協共済連、大学生協東京ブロックから合計11名が参加しました。冒頭、会議の参加者が一堂に会すのと同等に十分な意見交換ができるかを相互に確認しました。
県生協連の中谷事務局長が進行役となり会議を進行しました。
◆会議内容
中谷事務局長が前回会議と事前打ち合わせ会議の報告を行いました。
〇大学生協共済連の大本氏より資料に沿って報告がありました。
・学生総合共済の加入状況と対策について
・新社会人コースの申し込み状況と対策について
・新社会人向けセミナーの開催提案について
2022年度春のジュニア加入者からの学生総合共済への加入の状況やジュニアコース加入者の進学者への対応
状況、学生総合共済加入推進の取り組み、全国の事例紹介などお話いただきました。また、大学生協のない大
学へのアプローチ事例や新社会人コースの魅力で、卒業前に学生総合共済への駆け込み加入の事例など、お聞
きしました。今後、2022年の11月には満期WEBがリリースされて卒業生向けの新社会人コースの案内に活
用できることなどの説明がありました。また、2023年に向けての取り組み提案もありました。
〇コープながの共済センターの上原氏より資料に沿って報告がありました。
学生総合共済PJをきっかけに、動画によるオンラインセミナーへの取り組みにチャレンジしたことや大学生
協と連携・協働して新しい取り組みができた事を積極的に受け止め、コープながのLPA(ライフプランアド
バイザー)さん達と一緒に取り組みを進められ、動画セミナーを実施できたことは今後の活動への自信にもつ
ながっていること。2022年度に向けては大学生協の学生さんとの対面での懇談会やセミナーの開催ができれば
良いと考えていること。また、コープながのの組合員向けのWEB講座にも今年5月にチャレンジして、今回の活動をきっかけに、コープながのLPAの活動の新しい形ができたことなどが報告されました。
〇信州大学生協の専務補佐の田島氏からは、卒業生向けのDMの発送からオンライン講座のスタートまで時間が
経過してしまい、卒業生対応では出資金の返還窓口にて改めて卒業生向けのWEB講座の案内チラシを作成し
て配布しました。そのことによりWEB講座の受講者が増えました。また、新社会人コースの加入に関する問い合わせ時に、「どこの地域生協に加入したら良いのか?」などの質問に的確に答えられない場面などがあり、事前の準備や学習の必要性も感じました。と同時にシステムとしての改善の余地があると感じました。
⇒コープ共済連の後藤さんからは、各都道府県単位ではそれぞれの地域生協の規模に応じて、紹介先の地域生
協の案内をしていると説明があり、また、大学生協共済連の大本さんからは、11月にリリースする「満期W
EB」では、様々な問い合わせに対応できる機能を搭載する予定で現在準備を進めている旨、説明がありました。
〇信大生協の関根専務からは、新社会人コースの資料請求や問い合わせは、卒業生本人からか、親からか?
⇒共済連の感触では、約6割が本人からの問い合わせで、約4割が親からの問い合わせの状況。
〇今年度の春の新入生の学生総合共済の加入状況としては、約65%と例年に比べて若干減ってが、ある程度原因
は分析できており、今回の取り組みとは別の原因が把握できています。その点を考えると、ほぼ例年通りの実績と評価できるとのことでした。
2022年度の活動としては以下の計画が提案されました。
今後、第2回学生総合共済PJ会議にて、上記の①~③について、具体化をしていくこととしました。
尚、次回の会議日程については、2022年7月13日(水)11時~12時でオンライン開催とすることとしました。
以上

2022年5月23日(月)14時00分より、オンライン会議システムにより、2022年度第1回長野県生協災害対策協議会が開催されました。コープながの、生活クラブ生協長野、こくみん共済coop、長野医療生協、上伊那医療生協、セイコーエプソン生協、信州大学生協、長野県高齢者生協、パルシステム山梨の9会員生協にて構成し、当日は、4会員生協と県生協連事務局の6名が参加しました。
冒頭に60分間ミニ学習会を開催しました。長野県社会福祉協議会まちづくりボランティアセンターの橋本昌之主査には、「台風19号での避難所・福祉避難所の実情や課題」と題して実際に2019年当時の避難所での支援活動や実情と課題についてお話いただきました。また、まちづくりボランティアセンターの徳永雄大主任には、「発災時の社協の動き」についてご講演をいただき、その後質疑応答をしました。
学習会後、災害対策委員会を開催しました。
※詳しくはこの学習会はアーカイブ動画でご視聴いただけます。
アーカイブ動画のURL:https://youtu.be/ZoEtqCYgMDw
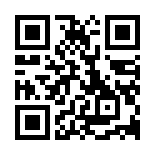
学習企画終了後、第1回災害対策協議会を開催しました。
<議題>
(1)委員長・副委員長の互選
委員長に川島宏夫(こくみん共済coop)、副委員長に中田義雄(コープながの)を選出し、川島委員長が議長に就任して議事を進行しました。
(2)≪報告事項≫
事務局が2021年度第2回長野県生協災害対策協議会の報告を行い確認しました。
(3)≪協議事項≫
事務局が2022年度 長野県生協災害対策協議会の活動方針について提案し、協議を行いました。協議の結果、
以下の内容を全員で確認した。
(4)≪意見交流≫
各生協の災害対応活動や新型コロナウィルス感染症の対応などの交流を行いました。
(5)その他
〇次回の会議は、2023年3月10日(金)14時~開催することを確認しました。
以 上