長野県内の生協のさまざまな活動・事業を紹介します。
長野県生協連では、2025年度の活動方針である能登半島地震被災地の復旧支援のため、「能登半島地震被災地視察と現地サロン活動」の第1回本企画を実施しました。本企画に先立ち、4月と5月に珠洲市を2度訪問し、現地の状況確認と関係者との打ち合わせを行いました。その後、7月にプレ企画を実施し、企画内容や行程を再検討し本企画実施に至りました。
今回は、県庁生協、生活クラブ生協長野、長野医療生協、こくみん共済coop長野推進本部、コープながの、県生協連から役職員、組合員理事の計12名が参加しました。7月のプレ企画参加者からの「現地の被災者との交流の場をもっと増やしてほしい」という意見を受け、本企画では、初日に被災地視察とNPO法人レスキューストックヤード(RSY)常務理事の浦野愛氏による講演・交流会を行い、2日目に現地サロン活動を実施するよう日程を変更しました。これにより、被災者との交流時間を増やすだけでなく、参加者の負担軽減も図ることができました。
浦野 愛常務理事からは、「令和6年能登半島地震 穴水町における支援活動」についてご講演いただき、RSYが2019年の台風19号災害における長野市豊野町での生活支援活動の経験が、今回の穴水町の支援活動にも繋がっていること、R6能登半島地震の災害関連死の要因の内訳や特徴、震災から1年半が経過した穴水町の現状、そしてRSYが発災後2日で現地(穴水町)入りし、支援の方策をゼロベースからどのように構築してきたかについて詳細かつ貴重な過程を説明いただきました。参加者からは、「現地で継続的に支援活動をされている団体の方々から、課題点と改善された点についてお話を伺うことができ、外部からは見えにくい支援活動の継続性の重要性を理解しました。」「リソースを自団体だけで賄うことの難しさと同時に、外部機関との連携が活動の拡張に繋がっていることを知り、縁と機会を大切にし、誠実に活動を続けることの重要性も感じました」といった感想が寄せられ、一般的な報道では伝わりづらい支援活動への理解を深めることができました。続いて、被災地視察と翌日に開催されるサロン活動会場周辺の仮設住宅へ訪問し、サロン参加の声掛けを行いました。

参加者からは、「広範囲に及ぶ被災地では、いまだに多くの方々が生活再建の目途が立たない状況にあることを知りました。」や、「特に、災害公営住宅で暮らす高齢者の方々が大変なご苦労をされていると、直接お話を伺い、胸が締め付けられる思いです」等の声が寄せられました。
第2日目のサロン会場には、27名の方にご来場いただきました。冒頭コープながの組合員理事の大原さんよりご挨拶をいただき、幕をあけました。
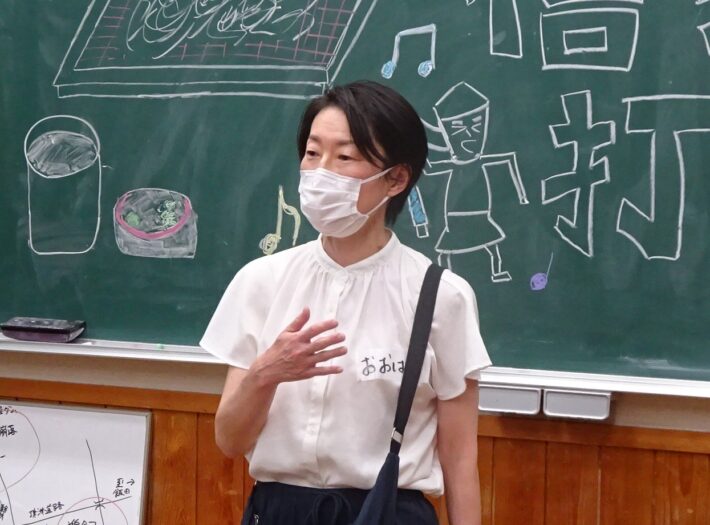
サロンでは「被災者との交流を深める」ことを重点に置き、「信州そば打ち(切り)体験」、「健康チェック」、「司法・行政書士相談」の企画にご希望に応じてご参加いただきました。「信州そば打ち(切り)体験」では、「水回し」「こね」「菊もみ」「へそ出し」と続き、生地を均一に広げてから麺棒で四角形に延ばし、最後に生地を畳んでから包丁で切るという本格的な工程を体験いただきました。切ったお蕎麦はお土産としてお持ち帰りいただき、厨房では前日に打ったそばを調理し、参加された皆様に振る舞いました。「本物の信州そばのおいしさを堪能してほしい」という思いから、出来上がったそばはすぐに召し上がっていただけるよう、連携プレーで頑張りました。


会場となった講堂では、6つのテーブルに分かれて、参加者が被災者の方々の間に座るなど、お一人おひとりに積極的に話しかけている様子が印象的でした。サロン活動の最後の企画として「みんなで歌おう」を実施し、リクエストに応えながら大きな歌声を響かせました。

被災者の方々からは、「お話ができて嬉しい」「遠いところから来てくれてありがとう」「楽しい時間をありがとう」といった温かいお言葉をいただきました。また、参加した役職員からは、「サロン活動の前は自分には大したことができないと思っていたが、話を聞くことや、そこにいて触れ合いをすることが、被災者の安心につながると感じ、自分にできることで与えられることがあることを感じるとても良い経験となった」「そば打ち体験では皆さん、真剣に他の人の作業にも注目して見ていて、とても楽しまれているように感じた」「歌では最後に手を繋いで輪を作るのは人の温もりを感じる良い取り組みだったと思う」といった感想が寄せられました。最後に生活クラブ生協長野の草野常務よりご挨拶があり、「引き続き被災された方々に寄り添い、交流を深める活動を続けながら、支援活動について考える場となればと思います」と締めくくられました。

