長野県内の生協のさまざまな活動・事業を紹介します。
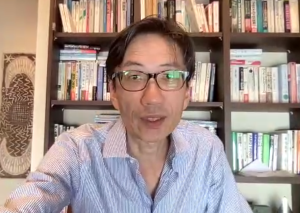
10月1日(土)に長野県生協連主催の長野県協同組合フェスティバル2022記念講演会、湯浅誠氏「地域共生社会づくり講演会」~誰もが生きやすい地域と社会を目指して、私たちにできることを学び、考える~を開催しました。110名を超える参加申し込みをいただき、オンライン企画としてYouTubeのライブ配信にて実施しました。長野県協同組合連絡会様の共催、長野県社会福祉協議会様・生活協同組合コープながの様・長野県消費者団体連絡協議会様・信州子ども食堂ネットワーク様・社会的養護出身の若者サポートプロジェクト様のご協力をいただき開催することができました。
冒頭、主催者を代表して太田会長のあいさつ、共催団体を代表して鈴木会長のあいさつの後、湯浅誠氏の講演が始まりました。認定NPO法人全国子ども食堂支援センター・むすびえ理事長で、社会活動家の湯浅誠氏には「こども食堂と私たちの地域・社会」と題して講演をいただきました。最初に、「社会づくり」とは、現在の社会からみんなが「目指す地域社会」への変更であり、今ある地域をより良くする活動と言える。そのよりよい社会(地域共生社会)のイメージを説明されました。相談支援では、相談窓口に来てくれた人に対して「断らない相談体制」や相談窓口に来られない人に対するアウトリーチができているか?の課題がある。次に参加支援では、相談の中で対象者をまるごと受け止めて参加につなぐ支援が難しい、それは8050問題でも80代の要介護の支援で訪問するケアマネが50代息子の支援を含めた対応ができない現状があり、多機関協働の連携がないと1機関・1担当だけでは対応が難しい課題がある。そして、出口支援としては地域づくりに向けた支援として、ニートや引きこもりの場合にはまずは体を動かす場、農作業などの場や就労支援、居住支援などが求められるが、そういう支援もやはり多機関協働の連携がないと支援まで結びつかないのが現状です。そういう地域社会づくりを考える時に、自分の地域はどこに課題があるのか?相談支援か、参加支援か、地域づくりにむけた支援かを考える。「うちの地域には人材がいない」という声をよく聞くがそういう時には「本当にそうなのか?」と3回じっくりと問いかけて考えてほしいとのこと。
次に、地域共生社会のイメージを子ども食堂の場を通して考えてみる。「こども食堂」とはどういう場か?市民が自発的に手弁当で作り上げている場で、現在全国で6000ヵ所以上あり、コロナ禍でも毎年1000ヵ所ずつ増えている活動。高齢者も参加ありが62.7%、参加に条件がないが78.4%、多世代交流が主たる目的が57.8%という場で人をタテにもヨコにも割らない(制限をしない)公園のような場所と言える。誰もが自由に参加して良い場所=わけへだてのない場所です。全世代が自由に参加しても良くて、困っている人や課題を抱えている人をみんなで支える場ではなくて、困っている人や課題を抱えている人をみんなで包み込む場所となっていることが大きな特徴であり、良さとも言える。困っている人を見つける場と言うよりも、あくまでもさりげなく気づいてあげて、安心していられると感じてもらえる場を作ること、つながりを多く作れる場であることが大切とのこと。
どんな地域社会にしたいのか?もっと人と人とが関わり合える地域にしたい!。少子高齢化の中で、何もしなければ自然と毎年1%ずつ地域は寂しくなっていくことが必然、そういう中で、毎年地域のつながりづくり・にぎわいづくりで「密」を2%ずつ増やしていく活動が、地域が「疎」になる大きな流れに抵抗していくことになる。 もう一つの側面として、多世代交流・地域交流型のセーフティーネットとしての機能が認められている。介護予防体操などの対象者であるハイリスク者が集いの場に参加している割合は、二次予防事業への参加者よりも2倍以上多いという事実。さて、【困っている人をみんなで支える地域】を目指すのか?、【みんなの中に困っている人を包み込む地域】を目指すのかのアプローチはとても似ているようで、違いがある。前者ではぶつかる壁は「支えてくれる人が増えない」壁であり、後者では気づきにくい(気づき力をつける)壁であるとのこと。今、自分たちはどちらのアプローチを進めていくのか?を知っておくこと、考えることが大切です。そういうことを考えながら、自組織の地域社会との関り方、活動を見つめ直して考えながら進めていくことが大切であると話されました。子ども食堂の活動を通して私たち自身は何を大切にして地域の課題に向き合っていくのかを改めて考える機会となるとともに、多くのヒントをつかむ機会になりました。

長野県協同組合フェスティバル2022年度第5回実行委員会が8月24日(水)11時00分からJAビル4階4B会議室・オンラインシステムにて開催され、13団体から19名が出席しました。定刻になり中谷事務局が開会を宣言し、実行委員会の関佳之事務局長があいさつと後、議事を進行しました。議事に先立ち参加者全員が一堂に会するのと同等に充分な意見交換ができることを相互に確認した。
協議事項
事務局が前回議事録の報告を行い、全員で確認しました。
事務局よりフェスティバルの開始時間を30分繰り上げて10時00分スタートする旨、提案があり協議を行いました。協議の結果、提案の通り承認しました。
事務局よりフェスティバルの開催又は中止の判断の基準及び万が一の中止判断のタイミングについて説明・提案があり、協議を行いました。協議の結果、提案の通り万が一の中止の判断は最終的に9月26日(月)まで慎重にコロナ感染状況などの情報を収集して事務局が決定することを確認しました。
一方、出展団体や実行委員会構成団体内の規定や事情により、出展辞退などの状況も予測されることを確認し、今後の各出店団体への連絡の中で、出展辞退の際の連絡の徹底についても案内することとしました。
事務局より、2022年度はコロナ禍でもあり、県及び長野市の来賓出席依頼や各構成団体の開会式への出席依頼を行わないということについて説明、提案があり協議を行った。協議の結果提案の通り確認しました。
事務局より、フェスティバルへの誘客対策として「当日チラシの5000枚作成」と「水風船の800個」を準備して、歩行者天国での配布と参加の呼びかけについて説明・提案があり協議を行いました。協議の結果提案内容を確認しました。
事務局よりアンケートの内容及びグーグルフォームによりアンケートの実施方法と景品との交換について説明・提案があり協議を行いました。協議の結果提案の通り確認をしました。尚、スマホによるアンケートの回答が困難な方には、紙のアンケート用紙をお渡ししてその場で回答いただくようにすることとしました。
事務局より前日及び当日の要員体制と作業内容について説明・提案があり協議を行いました。協議の結果提案の通り確認をしました。特に当日の搬入時と搬出時には出展者の車が混雑することが予想されることから、手伝いが可能な実行委員は各出展者の搬入のサポートを行うことを確認しました。
会場レイアウトを確認しました。
広報用告知チラシの原稿について確認をしました。修正希望がある場合は本日中に事務局に連絡を行うこととしました。26日から印刷を行い、31日までに各実行委員団体に納品することを確認しました。
事務局より各構成団体及び出展団体の活動紹介動画などの情報発信の方法について説明・提案があり協議を行いました。協議の結果、提案の通り確認をしました。
・出展者向けの駐車場の案内として出展者に配布する説明のチラシを確認しました。
・会場での掲示物について説明があり、確認をしました。
・ごみの持ち帰りについて、出展者と来場者に案内を行うことを確認しました。
・善行寺表参道秋まつりの実行団体との広報の協力と費用負担について説明を行い、全体の費用が見えてきた段階で5万~10万の範囲で協力をすることを確認しました。
・各出展者に配布する案内文書について提案があり、内容を確認した。内容には、出展辞退の状況が発生した場合の対応についても記載することとしました。
出店一覧表の確定版について確認をしました。
第6回実行委員会 11月8日(火)11時~12時 オンライン開催(フェスティバルのまとめなど)
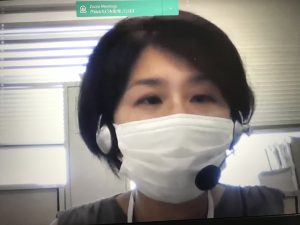
8月19日(金)に2022年度長野県生協連主催の理事長・専務理事懇談会がオンラインで開催され、12会員生協と理事、事務局、講演講師も含めて27名の参加で開催されました。
理事長・専務理事懇談会は、冒頭太田栄一会長理事の開会挨拶で始まりました。
学習講演会では長野県県民文化部子ども若者局長の野中祥子さんをお招きして、「子どもたちの未来と地域社会の課題」と題して、お話しいただきました。初めに、長野県の子ども・若者支援総合計画の概要をご説明いただき、長野県での初めての子ども・若者分野の横断的・一体的な支援計画として作成され、本年度が最終年度で、次期計画の作成中とのこと。実態把握や子育て支援や困難を有する子ども・若者・家庭へのきめ細やかな取り組みを推進。次に、子ども・若者を取り巻く状況について、コロナ禍での家事時間の増加や結婚・出産数の減少があり、理想の子どもの数が平均2.16人に対して、実際に持つつもりの子どもの数が平均1.41人とギャップがある。経済的負担や年齢的理由が主な理由です。ここ20年の数値でも20代~30代の若年層で低所得化傾向があり、子育て期の非正規割合も全国平均以上という状況です。また、コロナ禍において、孤立・孤独の顕在化、デジタル化の加速によりSNSに起因するトラブルや犯罪被害、誹謗中傷などの弊害、ゲーム依存などが指摘されている。
長野県としては、今後の更なる少子化対策に向けて、県と市町村が一体となって行う若者や子育て世代への支援について、本年3月25日に長野県知事・長野県市長会長・長野県町村会長の3者が行った「若者・子育て世代応援共同宣言」について説明があり、その中では、県民への呼びかけとして「次代を託す子どもたちの夢や若者や子育て世代の皆さんの希望を、私たちとともに、社会全体で支えるため、それぞれができることから行動を起こしていただきますようお願いいたします。」との発信がされたことの紹介がありました。また、長野県若者・子育て世代応援プロジェクトの取り組みも紹介され、「女性や若者が暮らしたくなる信州づくり」、「若者の出会いや結婚の希望の実現」、「子どもを生み、育てる世代の安心と幸せの実現」の3つの柱でそれぞれの取り組みについて詳しくご説明いただきました。
最後に、次期長野県子ども・若者支援総合計画についてめざす姿・主な施策のイメージのご説明をいただきました。学び、結婚、子育て、就労に対する希望への平等なアクセスとチャンスがある。子どもや若者が置かれた環境であきらめない、いつでもチャレンジができる。違いを認め合い、つながりあえるというイメージに向けて、それぞれを実現する施策の内容の説明もされ、今後次期計画を推進していく上での、今後の連携協働についても、前向きにメッセージをいただきました。
その後、会員生協の報告と交流が行われました。生活クラブ生活協同組合長野の千村康代理事長からは、FEC+Wのキーワードのご説明、自給と循環を大切にして持続可能な社会づくりと他団体との協働を重視していることのお話がありました。上伊那医療生協の根本賢一専務理事からは、コロナとの戦いの日々の活動や月2回開催しているなんでも相談会やおたすけ会の活動など、行政や社協とも連携した活動もご紹介いただきました。長野県労働者共済生協(こくみん共済coop)の川島宏夫次長からは、保障の生協として全国の連合会との協同の取り組みの紹介や毎年実施しているタオルの寄贈、交通安全を願っての7歳児への横断旗の寄贈やなわとびの寄贈の活動、フードバンク信州への支援活動などをご紹介いただきました。それぞれ短時間での報告でしたが、それぞれの生協の特徴がよくわかる報告で相互の理解が深まる時間となりました。最後に関佳之専務理事の閉会の挨拶があり、懇談会は終了となりました。

2022年8月19日(金)15時00分からから長野県生活協同組合連合会事務所(長野市)及びWEB会議システムにより第3回理事会が開催され、会長・副会長を含め理事13名、監事2名が本理事会に出席しました。
なお、議事に先立ち理事会参加者全員が一堂に会するのと同等に充分な意見交換ができることを相互に確認しました。以下の議題が承認、確認されました。
15時00分、関佳之専務理事が開会を宣言し、太田栄一会長理事が挨拶を行い、理事会規則第7条により議長に関根明副会長理事が選任され、議事に入りました。15時45分にすべての議事を終了し閉会しました
≪議決事項≫
関専務理事より第15次中期方針(県生協連)の策定に関する件について提案があり、協議を行いました。協議の結果、提案の通り承認しました。
関専務理事より役員推薦委員選任の件について説明、提案があり協議を行いました。協議の結果、提案の通り承認しました。
中谷事務局長より「2022年度長野県地域福祉コーディネーター総合研修」後援の件について説明、提案があり、協議を行いました。協議の結果、提案の通り承認しました。
≪協議事項≫
協議事項なし
≪報告事項≫
以下の事項を事務局が報告し、了承しました。
1.機関会議等報告
(1)第2回理事会
(2)第2回常任理事会
(3)7月決算概況
2.その他報告
(1) 信州協同ネットフォーラム(日本労協新聞)
(2)各種研修会・懇談会の開催に関する件
別冊資料により上期の学習・研修企画の報告、参加者アンケートの共有を行い、12月上旬に計画して
いるボランティアコーディネーション3級検定試験の長野県社協との共催について報告がありました。
また、新井理事より、長野県社協主催の信州ふっころフェスティバルやまちづくりボランティアフォ
ーラムについての質問があり、2022年度から両企画の実行委員会に参加しており、信州ふっころフェ
スティバルは11月に、長野県まちづくりボランティアフォーラムは12月に開催予定であり、開催案
内などができたら、各会員生協へも案内を行う旨、回答がありました。
(3)湯浅誠さんの講演会企画に関する件
(4)会員活動担当者交流会
(5)県連ニュース
(6)令和4年度指導検査(長野県)について
(7)長野ネットニュース
(8)ながネットに関する件
3.情報提供
(1)中央地連県連活動推進会議(日生協)
(2)2022年8月豪雨被災地支援活動ニュース(日生協)
(3)組活ニュース(日生協)
(4)復興支援&防災ニュース(日生協)
(5)フードバンク&フードドライブニュース(日生協)
以上をもってすべての議事を終了し、議長が15時45分に閉会を宣言しました。

2022年8月4日(木)9時00分よりオンラインにて会員活動担当者交流会を開催し、コープながの、こくみん共済coop、住宅生協、松本大学生協、事務局より5名が出席しました。冒頭、事務局が開会挨拶を行い、その後、交流会の議事を進行しました。
なお、議事に先立ち実行委員参加者全員が一同に会するのと同等に十分な意見交換ができることを相互に確認し、全員が自己紹介を行った後に議事に入った。
◆会議内容・議題
1.2022年度の上期の振り返り
・事務局が上期の企画について報告を行い、意見交換をしました。
・アーカイブの共有は、当日欠席者にはとても良い方法だが、視聴期間はできるだけ長く設定して欲しい。
・憲法学習会はとても良い企画でした。今後大切な内容でもあり、今後継続した学習の場づくりが必要と思う。
などの意見が出されました。
2.会員交流
各参加者から以下のような報告がありました。
〇コープながの:8月8日からインスタグラムをはじめます。「ヒロシマ・ナガサキ 原爆と人間」パネル展を県内4会場で開催予定。コープながのでは合計4セット保有していますので、各生協でも貸し出しを受け付けていますので、要望のある生協はお声がけください。
9月12日(月)10時00分~11時40分に「満蒙移民」の歴史に学ぶ(阿智村・満蒙開拓平和祈念館を訪ねる前に知っておきたいこと)の学習会をオンライン企画で開催します。どなたでもご参加できますので、希望の方はお申込み下さい。
〇こくみん共済coop:7/29総会終了。長野県内の小学一年生向けに横断旗の寄贈を各教育委員会へ提案をして、必要な学校からリクエストをいただき寄付をします。また、長野県のスポーツ課経由で、県内小学校になわとびの寄贈を提案して希望校を集約しています。
〇大学生協:以前から自転車の無料点検や食生活相談会などを実施してきました。今後、学生組合員に提案したい学習機会としては「松代地下壕の見学」、「子どもの人権宣言関連(ユニセフ)」、「災害ボランティアに関する学習会」などはニーズもあります。公務員講座(就職対策セミナー)などをしていると、ボランティアぐらいしていないと就職できないという空気がある。
交通安全のために自転車無料点検などを組合員向けに実施している。←こくみん共済coopでは自動車運転シミュレーターや自転車運転シミュレーターを保有しています。
労働金庫は松本大学と県立大学で卒業生向けのDMを発送している。
⇒9月1日の県の図上訓練、9月19日の信州大学防災減災フェアー(長野市のセントラルスクゥエア)の紹介が事務局からあり、9/19の企画は後日案内することとしました。
〇住宅生協:以前は労金と一緒に住宅フェアを実施していました。対面での相談会の形式で、コロナ禍の実施が難しい状況です。
3.2022年度9月以降の学習会や研修会企画について
・事務局より、2022年度9月以降の現在予定されている学習会・研修企画について報告を行いました。
・現在予定されている概要を説明し、意見交換を行いました。
・レジュメ記載以外にも9/8ファシリテーション講座(フォローアップ編)、2023年2月頃に県労福協主催の
みらい・あんしん学校などの情報を共有しました。
・9月以降の学習・研修企画については、可能なものはできるだけアーカイブ配信を行うことを確認しました。
・コープながのでは、食の安全学習会(ゲノム編集食品関連)の予定あります。
・日本生協連でWWFの学習会があったが、次年度でも県生協連主催で同様の学習会ができると良い。
・大学生協からは、長野県の「しあわせ信州創造プラン2.0」のような、行政の計画を学ぶ学習会や、農業生
産県として生産者が見える学習会、防災や災害ボランティアを学ぶ学習会、教育学部の学生向けには、子育
てや教育に関する学習会などがあると参加呼びかけができるとの意見がありました。
・ボランティアコーディネーション力検定の実施(共催)の提案について説明をして協議を行った。初めて行
う検定でもあり、会員生協への丁寧な説明を行うことを合わせて確認しました。
・10月1日の長野県協同組合フェスティバル記念「湯浅誠講演会」、11月25日第52回長野県消費者大会、長
野県社協の地域福祉コーディネーター総合研修については、資料により共有しました。
・今後、月に1回程度の頻度で会議を開催し、次回会議には秋以降の具体的な学習会計画を提案して、協議を
進めていく事を確認した。尚、次回以降の日程については、他のメンバーも含めて、調整をして決めること
としました。
4.その他
〇次回以降の会議日程は後日調整をして案内をすることとしました。